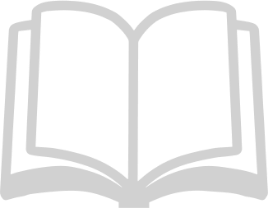大絶画さんの公開ページ レビュー一覧
レビュー
ユングはどこかで「ニーチェの分析をしてみたい」と書いていたそうですが、論文等で言及するのみでまとまった著作にはなっていなかったはずです。それはニーチェを襲った集合的無意識の強大さを感じ取っていたからかもしれません。
そして師の仕事は弟子に受け継がれました。ユング心理学を学ぶ前、ウェーバーや社会学を研究していた林氏は適任といえるでしょう。氏はその後『元型論』や『タイプ論』の翻訳を担当します。
さて『ツゥラトゥストラ』を読んだ方は3・4部の異常な雰囲気に圧倒されるでしょう。氏はそこに集合的無意識の発露を見出します。ニーチェは個人の意志で集合的無意識に対抗しました。しかしその末路が悲劇で終わることは必然です。そしてその悲劇はニーチェのみならずナチス・ドイツという形で引き継がれます。
序文で著者が語っているようにやや型通りにユング心理学を適用した嫌いはあります。とはいえ『ツゥラトゥストラ』の分析を通していかに無意識と調和するか、これは20世紀のドイツ人のみならず21世紀を生きる我々にも有益と考えます。
2026/02/01
ユングはどこかで「ニーチェの分析をしてみたい」と書いていたそうですが、論文等で言及するのみでまとまった著作にはなっていなかったはずです。それはニーチェを襲った集合的無意識の強大さを感じ取っていたからかもしれません。
そして師の仕事は弟子に受け継がれました。ユング心理学を学ぶ前、ウェーバーや社会学を研究していた林氏は適任といえるでしょう。氏はその後『元型論』や『タイプ論』の翻訳を担当します。
さて『ツゥラトゥストラ』を読んだ方は3・4部の異常な雰囲気に圧倒されるでしょう。氏はそこに集合的無意識の発露を見出します。ニーチェは個人の意志で集合的無意識に対抗しました。しかしその末路が悲劇で終わることは必然です。そしてその悲劇はニーチェのみならずナチス・ドイツという形で引き継がれます。
序文で著者が語っているようにやや型通りにユング心理学を適用した嫌いはあります。とはいえ『ツゥラトゥストラ』の分析を通していかに無意識と調和するか、これは20世紀のドイツ人のみならず21世紀を生きる我々にも有益と考えます。
2026/02/01
ヤスパース哲学の魅力は様々でしょうが、一つ特長を挙げるなら「交わり」の概念に代表されるように常に外部に開かれていることでしょう。
それはヤスパースの序文で二人の仕事ぶりを賞賛しつつも「一つの骨格に還元されてしまったことを残念に思う」と書きつつも「読者が私の著作に接近しやすく」と受け容れていることからも理解できるでしょう。
本作で取り扱われているのは前期ヤスパース哲学の『哲学』と関連する『理性と実存』『実存哲学』までです。しかしヤスパース哲学を支障はないでしょう。また佐藤氏をはじめとした訳者の仕事ぶりも素晴らしく大著『哲学』に挑む際、参考になるはずです。
なお解説によればデュフレンヌ、リクールともに後にヤスパースから離れていきますが、ヤスパースの基盤をしっかり受け継いだということです。どうか開かれたそして重厚なヤスパース哲学を堪能して下さい。
2025/12/29
ヤスパース哲学の魅力は様々でしょうが、一つ特長を挙げるなら「交わり」の概念に代表されるように常に外部に開かれていることでしょう。
それはヤスパースの序文で二人の仕事ぶりを賞賛しつつも「一つの骨格に還元されてしまったことを残念に思う」と書きつつも「読者が私の著作に接近しやすく」と受け容れていることからも理解できるでしょう。
本作で取り扱われているのは前期ヤスパース哲学の『哲学』と関連する『理性と実存』『実存哲学』までです。しかしヤスパース哲学を支障はないでしょう。また佐藤氏をはじめとした訳者の仕事ぶりも素晴らしく大著『哲学』に挑む際、参考になるはずです。
なお解説によればデュフレンヌ、リクールともに後にヤスパースから離れていきますが、ヤスパースの基盤をしっかり受け継いだということです。どうか開かれたそして重厚なヤスパース哲学を堪能して下さい。
2025/12/29
雄山閣より刊行された新版『ダキニ天信仰と俗信』のレビューです。
ダキニ(ダーキニー、荼吉尼天)のオリジンは地母神ダーキンとされます。その後、暗黒神マハーカーラ(大黒天)の眷属となり、日本においては「狐が化かす」ことからダキニは悪神・邪神と結びつくようになりました。
マハーカーラが大国主命と結びつき福の神・大黒様となったことを考えると大きな違いです。
著者はダキニのルーツをたどりつつダキニの復権を望んでおられます。本書の復刊がダキニ信仰につながるよう語り継ぎましょう。
2025/12/06
本件はGOTより刊行された新装版『イヴとイヴたち』のレビューです。
百合姫判に比べサイズが小さくなっていますが、2作の作品が追加で収録されトータルではお得になっているはずです。何よりも電子配信もなくなっていたので再び読めることが一番でしょう。
さて著者は主に成人向け作品で活躍されており(2作品が元々成人向けアンソロジーに収録されたもの)、先生が連載されていた頃から『百合姫』誌上でもアダルティな描写が増えたように思います。
そういった記念碑的な作品であることももちろんですが、百合SF・日常系百合としても楽しめる作品が多いので、ぜひ手に取って下さい。
2025/12/06
本件はGOTより刊行された新装版『イヴとイヴたち』のレビューです。
百合姫判に比べサイズが小さくなっていますが、2作の作品が追加で収録されトータルではお得になっているはずです。何よりも電子配信もなくなっていたので再び読めることが一番でしょう。
さて著者は主に成人向け作品で活躍されており(2作品が元々成人向けアンソロジーに収録されたもの)、先生が連載されていた頃から『百合姫』誌上でもアダルティな描写が増えたように思います。
そういった記念碑的な作品であることももちろんですが、百合SF・日常系百合としても楽しめる作品が多いので、ぜひ手に取って下さい。
2025/12/06
柴山師は禅的体験をしばしば「深い絶望を超えるような体験」とおっしゃっています。またいたずらに公案を思弁的・倫理的に解釈することを戒めています。
本書はもともとアメリカの知識層に向けた提唱が元になっています。たとえば一見すると罵倒としか思えない無門師の先師への賞賛であり、禅の初心者が躓くであろう部分を補足していますが、決して回答が示されていません。それは読者が全存在を傾けて導き出すものでありましょう。
『無門関』の解説書はいくつかあります。自分の師や宗派に合せて選ぶのがベストとは思いますが、そういった縁のない方は本書を手にするのがいいでしょう。どうか一筋の光が得られんことを。
2025/08/27
柴山師は禅的体験をしばしば「深い絶望を超えるような体験」とおっしゃっています。またいたずらに公案を思弁的・倫理的に解釈することを戒めています。
本書はもともとアメリカの知識層に向けた提唱が元になっています。たとえば一見すると罵倒としか思えない無門師の先師への賞賛であり、禅の初心者が躓くであろう部分を補足していますが、決して回答が示されていません。それは読者が全存在を傾けて導き出すものでありましょう。
『無門関』の解説書はいくつかあります。自分の師や宗派に合せて選ぶのがベストとは思いますが、そういった縁のない方は本書を手にするのがいいでしょう。どうか一筋の光が得られんことを。
2025/08/27
一部の宗派を除き仏教では「戒(律)・定(禅)・慧」の三学兼修が求められます。真言宗で重用される『菩提心論』でも「三昧地(禅定)に達することで即身成仏(生身のまま覚りを得る)できる」と説かれ、尊者自身、道場観(密教の瞑想法)を通し自らの過ちに気付かれました。禅への関心は深く禅宗との交流もありました。
尊者が禅宗で重用される『金剛経』の講義を行ったのも当然でしょう。一段一段、仏典のみならず儒教や神道の経典を駆使して読み解いておられます。一見すると密教と無関係とも思われますが「すべての文字の中に仏教の教え(大日如来の声)が宿っている」という空海様の教えを思わせます。
密教と禅宗の融和が本作に示されているように思います。
2025/08/24
一部の宗派を除き仏教では「戒(律)・定(禅)・慧」の三学兼修が求められます。真言宗で重用される『菩提心論』でも「三昧地(禅定)に達することで即身成仏(生身のまま覚りを得る)できる」と説かれ、尊者自身、道場観(密教の瞑想法)を通し自らの過ちに気付かれました。禅への関心は深く禅宗との交流もありました。
尊者が禅宗で重用される『金剛経』の講義を行ったのも当然でしょう。一段一段、仏典のみならず儒教や神道の経典を駆使して読み解いておられます。一見すると密教と無関係とも思われますが「すべての文字の中に仏教の教え(大日如来の声)が宿っている」という空海様の教えを思わせます。
密教と禅宗の融和が本作に示されているように思います。
2025/08/24
何からニーチェに入るかは人それぞれですが、後期ニーチェ思想は始まりであり主著『ツァラトゥストラ』とも関連が深い『喜ばしき知恵』が一番かもしれません。
内容も(回復期だったせいか)伸び伸びとしておりアフォリズム(断章)ですのでどこから読んでもいい。125番の「神の死」がそれ以外のアフォリズムも面白う。
さて本作はちくま学芸文庫・信太訳『悦ばしき知識』や講談社学術文庫・森訳『愉しい学問』などがありますが、河出文庫・村井訳は訳注がほとんどなく本文を読むだけで内容がこなれておりお勧めです。
2025/08/04
中公文庫で『マヌ法典』の翻訳を担当した著者による解説書です。
現在でもインドの8割はヒンドゥー教徒が占めており、3000年以上インドの生活規範を支配してきた『マヌ法典』(をはじめとしたダルマ法典)の理解なくしてインドの理解はできません。
さて本書では歴史的背景や法典の内容を通してヒンドゥー教世界の理解を促していきます。現在でも30以上の言語、1000以上の方言があるとされるインドが一つの国としてまとまっているのも『マヌ法典』をはじめとした規範があったからでしょう。もちろん現在も根深く残るカースト制度など負の影響もありますが、逆説的にITの発展につながりました(下位のカーストが法典にない仕事に集中したため)。
2023年インドの人口は14億人以上、中国を超え世界一になりました。今後、世界はインドの市場を狙うことは間違いありません。しかしカーストの問題そしてパキスタン(イスラム教圏)との対立と問題はあります。インドに対しどのようなスタンスを取るにせよ、背後のヒンドゥー教世界を理解する必要があります。本書はその助けとなるでしょう。
2025/06/22
中公文庫で『マヌ法典』の翻訳を担当した著者による解説書です。
現在でもインドの8割はヒンドゥー教徒が占めており、3000年以上インドの生活規範を支配してきた『マヌ法典』(をはじめとしたダルマ法典)の理解なくしてインドの理解はできません。
さて本書では歴史的背景や法典の内容を通してヒンドゥー教世界の理解を促していきます。現在でも30以上の言語、1000以上の方言があるとされるインドが一つの国としてまとまっているのも『マヌ法典』をはじめとした規範があったからでしょう。もちろん現在も根深く残るカースト制度など負の影響もありますが、逆説的にITの発展につながりました(下位のカーストが法典にない仕事に集中したため)。
2023年インドの人口は14億人以上、中国を超え世界一になりました。今後、世界はインドの市場を狙うことは間違いありません。しかしカーストの問題そしてパキスタン(イスラム教圏)との対立と問題はあります。インドに対しどのようなスタンスを取るにせよ、背後のヒンドゥー教世界を理解する必要があります。本書はその助けとなるでしょう。
2025/06/22
『般若心経』は何を説いたお経か?著者は「観想(瞑想)のプロセス(階梯)を明らかにしている」と説きます。
一見すると既存の仏典を否定しているかのように見える経文も、サンスクリット語のテキストを読む込むことで、それまでの仏陀の教えを肯定している。それはすべての仏教を包括する教えといっても過言ではないでしょう。さらにおよそ1400年前に空海が『般若心経秘鍵』が同じ結論に達していたのも驚くべきことです。
さて大きな書店に行けば棚の1・2列、般若心経関連の著作が占拠していることも珍しくありません。自分のレベルや宗派に合せて選ぶのが一番とは思いますが、サンスクリット語テキストから理解したという方は本書がベストだと思います。
2025/06/22
『般若心経』は何を説いたお経か?著者は「観想(瞑想)のプロセス(階梯)を明らかにしている」と説きます。
一見すると既存の仏典を否定しているかのように見える経文も、サンスクリット語のテキストを読む込むことで、それまでの仏陀の教えを肯定している。それはすべての仏教を包括する教えといっても過言ではないでしょう。さらにおよそ1400年前に空海が『般若心経秘鍵』が同じ結論に達していたのも驚くべきことです。
さて大きな書店に行けば棚の1・2列、般若心経関連の著作が占拠していることも珍しくありません。自分のレベルや宗派に合せて選ぶのが一番とは思いますが、サンスクリット語テキストから理解したという方は本書がベストだと思います。
2025/06/22
『偶像の黄昏』『アンチクリスト』ともにニーチェ最晩年の作品です。筆が乗っていたのか毒舌タレントの批評を聞いているような気分にすらなります。しかし2年後、ニーチェは狂気の深淵に沈むことになります。
彼はこれらの作品で西洋の価値観とくにキリスト教道徳を否定していますが、むしろニーチェにこそキリスト教道徳が必要だったのかもしれません。彼自身、キリスト教道徳を否定してもキリスト(イエス)そのものは否定していないように思えます。そもそも彼自身、自らが依って立つ価値観を壊して生きられるほどの「超人」ではなかったのです。
皮肉にも西洋的価値観を破壊するために振り下ろされた鉄槌はニーチェ自身を砕くことになりました。本書の読者はくれぐれも注意されますよう。
最後に西尾氏の翻訳に触れます。簡単な注は()で挿入されており、文体もふてぶてしさを感じられ、ある種の心地よさすらあります。ぜひ書店などで読み比べて自分に合ったものをお選びください。
2025/05/05
『偶像の黄昏』『アンチクリスト』ともにニーチェ最晩年の作品です。筆が乗っていたのか毒舌タレントの批評を聞いているような気分にすらなります。しかし2年後、ニーチェは狂気の深淵に沈むことになります。
彼はこれらの作品で西洋の価値観とくにキリスト教道徳を否定していますが、むしろニーチェにこそキリスト教道徳が必要だったのかもしれません。彼自身、キリスト教道徳を否定してもキリスト(イエス)そのものは否定していないように思えます。そもそも彼自身、自らが依って立つ価値観を壊して生きられるほどの「超人」ではなかったのです。
皮肉にも西洋的価値観を破壊するために振り下ろされた鉄槌はニーチェ自身を砕くことになりました。本書の読者はくれぐれも注意されますよう。
最後に西尾氏の翻訳に触れます。簡単な注は()で挿入されており、文体もふてぶてしさを感じられ、ある種の心地よさすらあります。ぜひ書店などで読み比べて自分に合ったものをお選びください。
2025/05/05
『修証義』は道元の主著『正法眼蔵』や仏典から編まれた全五章三十一節の文章です。
本書は一節一節である原典である『正法眼蔵』に立ち帰り解説しており、著者は西洋哲学を専攻していたこともあってグローバルな視点で『修証義』を読み解いています。曹洞宗の常用経典という位置づけではありますが、内容は仏教入門であり私のような他宗派にも得るものが多いでしょう。とくに道元が坐禅する(真摯に生きる)姿に仏を見出したことに納得がいきます。
この度、法蔵文庫に収録され日用の合間にも見直せるようになりました。行住坐臥(日常生活)すべてが修行と思い、折に触れて確かめるのがいいでしょう。
2025/04/11
『修証義』は道元の主著『正法眼蔵』や仏典から編まれた全五章三十一節の文章です。
本書は一節一節である原典である『正法眼蔵』に立ち帰り解説しており、著者は西洋哲学を専攻していたこともあってグローバルな視点で『修証義』を読み解いています。曹洞宗の常用経典という位置づけではありますが、内容は仏教入門であり私のような他宗派にも得るものが多いでしょう。とくに道元が坐禅する(真摯に生きる)姿に仏を見出したことに納得がいきます。
この度、法蔵文庫に収録され日用の合間にも見直せるようになりました。行住坐臥(日常生活)すべてが修行と思い、折に触れて確かめるのがいいでしょう。
2025/04/11
大乗仏教といえば『維摩経』に代表されるように寛容的・在家重視の思想を思い浮かべるかもしれません。しかし本書に収録されている三経典は禁欲的・出家重視の内容になっています。空観や本生譚がなければ原始仏典を思い浮かべるかもしれません。
しかしどちらも間違いではなく、それぞれの立場で「我らこそ仏教の正統(大乗仏教)である」と宣揚したといえます。そして『維摩経』や『法華経』を補完する作品群といえるでしょう。
一般的な大乗仏典は甘いと考える方にお勧めです。
2025/03/23
法華経とくに鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』は『般若心経』に次いで読まれた経典であり、『維摩経』と並ぶ仏教文学の最高峰、アジア思想にも影響を与えてきました。サンスクリット(梵)語原典を現代語訳で読みたいという方も多いと思います。
さてサンスクリット語原典の現代語訳としては岩波文庫の坂本・岩本訳、岩波書店の植木訳は手に入りやすいです。前者が歴史的背景が押さえてあり・羅什訳との対比が便利ですが文法に間違いがある。植木訳は文法が確かで掛詞もしっかり訳されていますが自説や自宗に対するこだわりが強いように思います。
そこで中公文庫版ですが羅什訳を中心にまとめつつも漢訳三本・梵訳・チベット訳と各種テキストを比較しており内容も確かで中立な訳になっています。注釈で歴史的背景や羅什訳との違いも押さえていますから、しっかりとサンスクリット語原典と向き合いたい方にお勧めです。
2025/03/15
法華経とくに鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』は『般若心経』に次いで読まれた経典であり、『維摩経』と並ぶ仏教文学の最高峰、アジア思想にも影響を与えてきました。サンスクリット(梵)語原典を現代語訳で読みたいという方も多いと思います。
さてサンスクリット語原典の現代語訳としては岩波文庫の坂本・岩本訳、岩波書店の植木訳は手に入りやすいです。前者が歴史的背景が押さえてあり・羅什訳との対比が便利ですが文法に間違いがある。植木訳は文法が確かで掛詞もしっかり訳されていますが自説や自宗に対するこだわりが強いように思います。
そこで中公文庫版ですが羅什訳を中心にまとめつつも漢訳三本・梵訳・チベット訳と各種テキストを比較しており内容も確かで中立な訳になっています。注釈で歴史的背景や羅什訳との違いも押さえていますから、しっかりとサンスクリット語原典と向き合いたい方にお勧めです。
2025/03/15
仏教とくに本経を含む般若経典には虚無主義・厭世主義という印象を持たれる方が多いと思います。しかし否定の否定(二重否定)が強い肯定を表わすように『理趣経』は密教の精神である生命の肯定を表わしています。
さて『理趣経』には「セックスを肯定したお経である」という印象を持つ方がいます。それは経文の表面をただ眺めるからで本質は世俗の欲望を超えた大楽の道を示しています。
本書では『理趣経』の歴史的な背景そして深層を解説し、ありのままの生命を肯定する密教の精神が説かれています。
現代では個人の欲望が肯定されます。しかし多くの人は我欲に振り回されることに疲れているはずです。いま一度『理趣経』に説かれている大楽(欲望を超えた欲望)を見直す時なのかもしれません。
2025/02/28
仏教とくに本経を含む般若経典には虚無主義・厭世主義という印象を持たれる方が多いと思います。しかし否定の否定(二重否定)が強い肯定を表わすように『理趣経』は密教の精神である生命の肯定を表わしています。
さて『理趣経』には「セックスを肯定したお経である」という印象を持つ方がいます。それは経文の表面をただ眺めるからで本質は世俗の欲望を超えた大楽の道を示しています。
本書では『理趣経』の歴史的な背景そして深層を解説し、ありのままの生命を肯定する密教の精神が説かれています。
現代では個人の欲望が肯定されます。しかし多くの人は我欲に振り回されることに疲れているはずです。いま一度『理趣経』に説かれている大楽(欲望を超えた欲望)を見直す時なのかもしれません。
2025/02/28
“白蓮華”と名がついたお経といえば『妙法蓮華経(白蓮華のような正しい教え)』が有名です。そしてもう一つの白蓮華の名がついたお経といえば本経『悲華経(白蓮華ような大悲の教え)』でしょう。
本経は浄土三部経とは逆に“穢土成仏”を説いています。それは浄土に産まれることが可能なのにあえて穢土を選んだ釈尊の大いなる慈悲が賛嘆されています。その様は壮絶の一言で優しい方は気分が悪くなるかもしれません。
とはいえ浄土の素晴らしさを知るためには穢土の悲惨さを知る必要があります。法然や親鸞が著書で再三引用したのもそのためです。
『妙法蓮華経』と並ぶ白蓮華(正法)『悲華経』を一度は読んでみましょう。
2025/02/23
“白蓮華”と名がついたお経といえば『妙法蓮華経(白蓮華のような正しい教え)』が有名です。そしてもう一つの白蓮華の名がついたお経といえば本経『悲華経(白蓮華ような大悲の教え)』でしょう。
本経は浄土三部経とは逆に“穢土成仏”を説いています。それは浄土に産まれることが可能なのにあえて穢土を選んだ釈尊の大いなる慈悲が賛嘆されています。その様は壮絶の一言で優しい方は気分が悪くなるかもしれません。
とはいえ浄土の素晴らしさを知るためには穢土の悲惨さを知る必要があります。法然や親鸞が著書で再三引用したのもそのためです。
『妙法蓮華経』と並ぶ白蓮華(正法)『悲華経』を一度は読んでみましょう。
2025/02/23
コンスタンティヌス(キルケゴール)によれば後方(過去)に向かうのが「追憶」で前方(未来)に向かうのが「反復」です。
かみ砕いていうなら苦しみや悲しみを受け入れつつ未来に向かって生きるということになでしょうか。本作ではコンスタンティヌスが青年の恋を通して「追憶」から「反復」への転換は可能を実験しているといえます。
いかなる結論が導かれるかは読者に委ねますが、本作を通してキルケゴールが「反復」したのはレギーネとの悲恋です。そういう意味で本作は『誘惑者の日記』の続編といえます。そして『反復』以後『不安の概念』や『死にいたる病』を書き上げますから彼は「反復した」といえるでしょう。
さて訳者は日本を代表するキルケゴール研究者で文庫版は翻訳と解説書を兼ねているといえます。実存文学の最高峰を名訳でお楽しみ下さい。
2025/02/16
コンスタンティヌス(キルケゴール)によれば後方(過去)に向かうのが「追憶」で前方(未来)に向かうのが「反復」です。
かみ砕いていうなら苦しみや悲しみを受け入れつつ未来に向かって生きるということになでしょうか。本作ではコンスタンティヌスが青年の恋を通して「追憶」から「反復」への転換は可能を実験しているといえます。
いかなる結論が導かれるかは読者に委ねますが、本作を通してキルケゴールが「反復」したのはレギーネとの悲恋です。そういう意味で本作は『誘惑者の日記』の続編といえます。そして『反復』以後『不安の概念』や『死にいたる病』を書き上げますから彼は「反復した」といえるでしょう。
さて訳者は日本を代表するキルケゴール研究者で文庫版は翻訳と解説書を兼ねているといえます。実存文学の最高峰を名訳でお楽しみ下さい。
2025/02/16
「なぜ私は不幸なのか」あるいはそこまでいかなくても「私はもっと幸福になれないか」と考える人は多いでしょう。
フィヒテによれば「本来『浄福(幸福)』と『生(存在)』は一致しているのにそれに気付いていないから」となります。そして明晰な思考でこの真理に到達する方法が説かれます。
さて本講話に限らずフィヒテの講話(『ドイツ国民への講話』など)は観念的・理想論的な傾向があります。そして何よりも彼の議論はキリスト教を前提としています。非キリスト教徒にとって取っ付きづらいのも事実でしょう。
とはいえ仏教の仏性論にも通じる彼の議論は、(私も含め)つい他人のあら探しや否定に終始する現代だからこそ輝くものです。人間の善性・理性を信頼したフィヒテの宗教論に耳を傾けましょう。
2025/02/01
「なぜ私は不幸なのか」あるいはそこまでいかなくても「私はもっと幸福になれないか」と考える人は多いでしょう。
フィヒテによれば「本来『浄福(幸福)』と『生(存在)』は一致しているのにそれに気付いていないから」となります。そして明晰な思考でこの真理に到達する方法が説かれます。
さて本講話に限らずフィヒテの講話(『ドイツ国民への講話』など)は観念的・理想論的な傾向があります。そして何よりも彼の議論はキリスト教を前提としています。非キリスト教徒にとって取っ付きづらいのも事実でしょう。
とはいえ仏教の仏性論にも通じる彼の議論は、(私も含め)つい他人のあら探しや否定に終始する現代だからこそ輝くものです。人間の善性・理性を信頼したフィヒテの宗教論に耳を傾けましょう。
2025/02/01
本書には密教の入口である『大日経』の住心品(序章)とその解説『大日経疏』第3巻まで。実践・功徳を説いた『理趣経』と解説『理趣釈』が収録されています。
本来、密教の奥義は師について学ぶべきものですが、「生きとし生けるものはすべて尊い存在である(即身成仏)」という精神。その真理に達するための「自分の心を知る(如実知自心)」という方法は学べます。
さて現代は高度情報化社会と呼ばれます。しかし実は自分のことすら知らないのが凡夫(凡人)である我々の実状です。今こそすべてを包括して理解する密教の精神を学ぶときなのかもしれません。
2024/12/28
「とりあえずキルケゴールの著作を読みたい」という方は本作を読むのが一番だと思います。分量も少なく現在でも優れた現代・大衆批判です。一般にキルケゴールの著作は人を寄せ付けない嫌いがありますが、本作は比較的読みやすい(しかし1度や2度では歯がたたない)でしょう。
さて『二つの時代』の文芸評論という形であぶり出された“現代”の姿は「分別(情報)はあるが情熱のない時代」になります。それはSNS時代の現在においてますます加速しているかもしれない。政治家・芸能人の発言や行動で一時期的に“炎上”するものの、それは半年もしないうちに有耶無耶になる。そしてそしてあれほど騒いだ事件の顛末がほとんどの大衆は気にもしない。
歴史初のマスコミ被害ともいうべき「コルサル事件」の被害者であったキルケゴールは身に染みたことでしょう。後にヤスパースやハイデッガーもキルケゴールの現代批判を継承します。
最後に国際報道などで「各国で極右・原理主義者への傾倒が見られる」と分析されることがあります。一見するとキルケゴールの指摘とは反対ですが、むしろ大衆は極右・原理主義へ均質(水平)化してるといえるのかもしれません。彼は『死にいたる病』をはじめ「信仰(神)と向き合うことで責任ある個人になれ」と説くのですが、神無き現代に可能なのか。現代でも彼の現代批判は普遍です。
2024/12/19
「とりあえずキルケゴールの著作を読みたい」という方は本作を読むのが一番だと思います。分量も少なく現在でも優れた現代・大衆批判です。一般にキルケゴールの著作は人を寄せ付けない嫌いがありますが、本作は比較的読みやすい(しかし1度や2度では歯がたたない)でしょう。
さて『二つの時代』の文芸評論という形であぶり出された“現代”の姿は「分別(情報)はあるが情熱のない時代」になります。それはSNS時代の現在においてますます加速しているかもしれない。政治家・芸能人の発言や行動で一時期的に“炎上”するものの、それは半年もしないうちに有耶無耶になる。そしてそしてあれほど騒いだ事件の顛末がほとんどの大衆は気にもしない。
歴史初のマスコミ被害ともいうべき「コルサル事件」の被害者であったキルケゴールは身に染みたことでしょう。後にヤスパースやハイデッガーもキルケゴールの現代批判を継承します。
最後に国際報道などで「各国で極右・原理主義者への傾倒が見られる」と分析されることがあります。一見するとキルケゴールの指摘とは反対ですが、むしろ大衆は極右・原理主義へ均質(水平)化してるといえるのかもしれません。彼は『死にいたる病』をはじめ「信仰(神)と向き合うことで責任ある個人になれ」と説くのですが、神無き現代に可能なのか。現代でも彼の現代批判は普遍です。
2024/12/19
プラトンの主著は質・量ともに『国家』でしょうが、影響力では『ティマイオス』が勝っています。
その内容はこれまでの著作と異なり神話的・オカルト的色彩が強く続編の『クリティアス』は未完に終わり『ヘルモクラテス』に至っては書かれずじまいです。
訳者解説の「もっともらしい言論」で言論の不安定さ・議論レベルの相違が指摘されてますが、これがプラトンが未完成に終わらせた原因かもしれません(そして長い間文庫化されなかった)。
しかし造物主デーミウールゴス(以下、長音略)がユダヤ教やキリスト教の唯一神と同一視され創造の神秘と説いたと考えられ、逆にグノーシス主義ではデミウルゴスこそ真の創造主と説かれました。また現代でもデミウルゴス、アトランティス、オリハルコン(アダマース)とオカルトや創作に生きています。
最後に講談社学術文庫版について述べると読みやすい文体で、読者が躓くであろう部分に解説が施されているように思えます。『クリティアス』が収録されていないことが残念ではありますが、プラトンの名著が文庫で読めるようになったのは画期的です。
2024/12/14
プラトンの主著は質・量ともに『国家』でしょうが、影響力では『ティマイオス』が勝っています。
その内容はこれまでの著作と異なり神話的・オカルト的色彩が強く続編の『クリティアス』は未完に終わり『ヘルモクラテス』に至っては書かれずじまいです。
訳者解説の「もっともらしい言論」で言論の不安定さ・議論レベルの相違が指摘されてますが、これがプラトンが未完成に終わらせた原因かもしれません(そして長い間文庫化されなかった)。
しかし造物主デーミウールゴス(以下、長音略)がユダヤ教やキリスト教の唯一神と同一視され創造の神秘と説いたと考えられ、逆にグノーシス主義ではデミウルゴスこそ真の創造主と説かれました。また現代でもデミウルゴス、アトランティス、オリハルコン(アダマース)とオカルトや創作に生きています。
最後に講談社学術文庫版について述べると読みやすい文体で、読者が躓くであろう部分に解説が施されているように思えます。『クリティアス』が収録されていないことが残念ではありますが、プラトンの名著が文庫で読めるようになったのは画期的です。
2024/12/14
「ほうれんそう(報告・連絡・相談)は大事だ」と1度ならず指導や研修を受けたでしょう。しかし元々社員でなく経営者の指針だったと知る人は少ないでしょう。
著者によれば「自分は浅才な経営者であり、経営を円滑に進める上で社員の叡智を結集する必要があった」と開発経緯を述べています。
さすがに初版が40年前のこともあり事例が古かったり終身雇用を前提とし現代に合わない部分はあります。しかし非正規労働者が増えた現代だからこそ社員の情報共有、"ほうれんそう"がスムーズに行える風通しのいい環境作りは必須と言えます。
最後に出版社の前書きからもわかるようにハラスメントやコンプライアンス違反など企業不祥事は後を絶ちません。とくに2023年は50・100年に1度レベルの不祥事が次々と明らかになりました。いま一度、土壌(企業風土)を見直して下さい。このままでは"ほうれんそう"どころかあなたの会社が立ち枯れてしまうかもしれません。
2024/09/07
「ほうれんそう(報告・連絡・相談)は大事だ」と1度ならず指導や研修を受けたでしょう。しかし元々社員でなく経営者の指針だったと知る人は少ないでしょう。
著者によれば「自分は浅才な経営者であり、経営を円滑に進める上で社員の叡智を結集する必要があった」と開発経緯を述べています。
さすがに初版が40年前のこともあり事例が古かったり終身雇用を前提とし現代に合わない部分はあります。しかし非正規労働者が増えた現代だからこそ社員の情報共有、"ほうれんそう"がスムーズに行える風通しのいい環境作りは必須と言えます。
最後に出版社の前書きからもわかるようにハラスメントやコンプライアンス違反など企業不祥事は後を絶ちません。とくに2023年は50・100年に1度レベルの不祥事が次々と明らかになりました。いま一度、土壌(企業風土)を見直して下さい。このままでは"ほうれんそう"どころかあなたの会社が立ち枯れてしまうかもしれません。
2024/09/07
本書では地蔵歎偈から地蔵三部経をはじめとした経典、そして霊験記や地蔵和讃と原典に忠実にそれでいてレベルを下げすぎず地蔵菩薩の偉大さを描いています。
読み進めていくうちに願王(悲願の王)と呼ばれる由縁が理解でき、お地蔵さまへの感謝も深まるはずです。
どうかお地蔵さまを見かけたら「南無地蔵菩薩」または「おん・かかか・びさんまえい・そわか」と唱えて下さい。六道の衆生を救うお地蔵さまにとって何よりの供養となります。
2024/09/05
坐禅の神髄を謳った文章は多々ありますが、白隠の「坐禅和讃」と道元の「普勧坐禅儀」が二大巨頭でしょう。
とくに「普勧坐禅儀」が道元が帰朝して初めて明らかにした文章であり、日本の坐禅はここから始まるといっていいのかもしれません。内容は人間の本質から、仏教(禅宗)の歴史、坐禅のやり方・心構えなど多岐に渡ります。しかし日本を代表する曹洞宗の僧であった著者が簡潔に説いておりますので、読み通せると思います。
最後に道元は「只管打坐(ただ坐禅せよ)」を唱えました。この「タダ」の奥深さ・難しさは本書の中で何度となく書かれています。しかしそれに臆することなく1日5分や10分でも、ぜひ坐禅を取り入れていただきたいです。道元の地平へ必ずたどり着けるはずです。
2024/08/07
坐禅の神髄を謳った文章は多々ありますが、白隠の「坐禅和讃」と道元の「普勧坐禅儀」が二大巨頭でしょう。
とくに「普勧坐禅儀」が道元が帰朝して初めて明らかにした文章であり、日本の坐禅はここから始まるといっていいのかもしれません。内容は人間の本質から、仏教(禅宗)の歴史、坐禅のやり方・心構えなど多岐に渡ります。しかし日本を代表する曹洞宗の僧であった著者が簡潔に説いておりますので、読み通せると思います。
最後に道元は「只管打坐(ただ坐禅せよ)」を唱えました。この「タダ」の奥深さ・難しさは本書の中で何度となく書かれています。しかしそれに臆することなく1日5分や10分でも、ぜひ坐禅を取り入れていただきたいです。道元の地平へ必ずたどり着けるはずです。
2024/08/07
護経(パリッタ)は大乗仏教の真言(陀羅尼)や念仏に相当するものです。仏教の実践が具体的に説かれています。
内容は「正しく観察しよう」とか「生きとし生けるものを慈しみましょう」など単純です。人によっては「きれい事」「理想論」と切り捨ててしまうかもしれません。ただ「素直に現状を受け止め、いまできることをしましょう」とも書かれています。
本書では1節(偈)ずつパーリ語原文・カタカナ表記・日本語訳が付き、さらに解説もされています。また巻末には対訳で経文が乗っています。単純ではありますが奥深い。1日1日読み進め実践していきましょう。
2024/08/04
龍樹をはじめとする中観派が言語(既成概念)の解体を通して執着からの解放(覚り)を目指したとするならば、世親たち瑜伽行唯識派は覚りや修行段階の言語化を目指したといえるでしょう。
彼らが取った手法は唯識すなわち「物事を認識している私はとりえず存在する」と認めることでした。それはデカルトの「コギト(我考える)」やフッサールの「判断中止(エポケー)」に通じる部分があります。
さて本書には世親による他派への反論である『唯識二十論』、『唯識三十頌』のスティマティ(安慧)の注釈『唯識三十論(釈)』、『三性論』と訳者・長尾氏の注釈と唯識の代表的な論書が収録されています。とくに中観と唯識の止揚を目指した『中辺分別論』が重要です。
講談社学術文庫『世親』と合せて読むことで唯識への理解が深まるはずです。
2024/07/27
龍樹をはじめとする中観派が言語(既成概念)の解体を通して執着からの解放(覚り)を目指したとするならば、世親たち瑜伽行唯識派は覚りや修行段階の言語化を目指したといえるでしょう。
彼らが取った手法は唯識すなわち「物事を認識している私はとりえず存在する」と認めることでした。それはデカルトの「コギト(我考える)」やフッサールの「判断中止(エポケー)」に通じる部分があります。
さて本書には世親による他派への反論である『唯識二十論』、『唯識三十頌』のスティマティ(安慧)の注釈『唯識三十論(釈)』、『三性論』と訳者・長尾氏の注釈と唯識の代表的な論書が収録されています。とくに中観と唯識の止揚を目指した『中辺分別論』が重要です。
講談社学術文庫『世親』と合せて読むことで唯識への理解が深まるはずです。
2024/07/27
龍樹は釈尊以後最大の理論家といえます。彼は大乗仏教の二大柱・中観(空観)を完成させました。彼が中観を通して訴えたかったものは何でしょう。
それは言語習慣(既成概念)の解体といっていいかもしれません。例えば「日本人」「共産主義者」など言葉を聞く発生するイメージがあるでしょう。そのイメージは適切でしょうか。あなたが勝手に作り上げた像ではないでしょうか。そしてその像が自縄自縛を引き起こしてはいないでしょうか。
龍樹は主著『中論』をはじめ「否定する対象が存在しないのだから否定しようがない」など言葉遊びのような言い回しで言語の解体を促します。独特の言い回し故、虚無主義や否定主義のレッテルを貼られましたが、何々主義からの解放こそ彼の望みです。
さて本書に『中論』は含まれていませんが、中観関連の論書、道徳書が収録されています。講談社学術文庫『龍樹』と合せて読むことで中観の理論・実践が理解できるはずです。
2024/07/26
龍樹は釈尊以後最大の理論家といえます。彼は大乗仏教の二大柱・中観(空観)を完成させました。彼が中観を通して訴えたかったものは何でしょう。
それは言語習慣(既成概念)の解体といっていいかもしれません。例えば「日本人」「共産主義者」など言葉を聞く発生するイメージがあるでしょう。そのイメージは適切でしょうか。あなたが勝手に作り上げた像ではないでしょうか。そしてその像が自縄自縛を引き起こしてはいないでしょうか。
龍樹は主著『中論』をはじめ「否定する対象が存在しないのだから否定しようがない」など言葉遊びのような言い回しで言語の解体を促します。独特の言い回し故、虚無主義や否定主義のレッテルを貼られましたが、何々主義からの解放こそ彼の望みです。
さて本書に『中論』は含まれていませんが、中観関連の論書、道徳書が収録されています。講談社学術文庫『龍樹』と合せて読むことで中観の理論・実践が理解できるはずです。
2024/07/26
坐禅の真髄を説いた書物は多々あれど真っ先に上げるべきは道元の『普勧坐禅儀』と白隠の『坐禅讃(坐禅和讃)』でしょう。
坐禅讃の歌い出しは「衆生本来仏なり」ですが「最初から仏ならばなぜ坐禅などするのか」と思われるかもしれません。本書は120ページほどの小著ですが、坐禅ににおける疑問や功徳・真髄が無駄なく説かれています。
まずは何より坐禅(あるいは白隠禅師の内観法)を始めるべきですが、時には禅師の坐禅讃を読み返してください。坐禅への熱意が強くなります。
2024/07/23
『ウパニシャッド』は古代インド思想の頂点でありヨーガや仏教にも肯定・批判的に受け継がれています。その重要性は疑うまでもないでしょう。
とはいえ素人が教典を読み通す並大抵ではありません。本来なら師について学ぶものですが、いい概説書がほしいところで、本書はその標準といえます。
さて本書ではウパニシャッドの研究史を眺めつつ、『ブリハッド』『チャーンドギヤ』『カウシータキ』など初期の主要ウパニシャッドの記述から本質に迫っていきます。
祭祀・儀礼からいかに高度な哲学が生まれたのか、なぜそのような思想が必要なのか理解できるはずです。
2024/07/19
現在はリスキニング(再学習)がささやかれています。そのためのアプリなど学習ツールも配信・販売されていますが、何よりも読書が基本でしょう。
さて著者は「学生時代のうちに読書の習慣をつける」よう書いています。また何を読むか・どのように読むか、簡潔ではありますが手堅くまとめられており読書論を学ぶ上で古典(スタンダード)といえます。
また読書論を超えて、師である西田幾多郎そしてハイデッガー(ハイデッゲル)など知識人との交流と知的好奇心を満たしてくれるでしょう。
2024/07/18
起心書房ハードカバー版のレビューです。
著者シャーンティデーヴァ(寂天)の主著は何といっても『入菩提(菩薩)行論』(以下BCA)でしょう。一般に『学処集成』(以下SS)の要約であるBCAが用いられますが(この点、親鸞の『教行信証』と『歎異抄』の受容に似ています)、寂天自身BCAの中で「詳しくはSSを読むように」と勧めています。
さてSSの内容は菩薩行の教則本と言っていいでしょう。多くの経典を引用しつつ菩薩の心構え・修行法を説いています。凡夫には難しい部分が多々ありますが、読み進めていくうちに心が浄化されるようです。
さてチベット仏教への関心からBCAそしてSSが注目されるようになりましたが、日中では漢訳である『大乗集菩薩学論』の出来の悪さもあってかあまり注目されることはありませんでした。サンスクリット語原典からの直訳である本作を通し大乗仏教(とくに中観派)の精神・行を学びましょう。
2024/07/08
起心書房ハードカバー版のレビューです。
著者シャーンティデーヴァ(寂天)の主著は何といっても『入菩提(菩薩)行論』(以下BCA)でしょう。一般に『学処集成』(以下SS)の要約であるBCAが用いられますが(この点、親鸞の『教行信証』と『歎異抄』の受容に似ています)、寂天自身BCAの中で「詳しくはSSを読むように」と勧めています。
さてSSの内容は菩薩行の教則本と言っていいでしょう。多くの経典を引用しつつ菩薩の心構え・修行法を説いています。凡夫には難しい部分が多々ありますが、読み進めていくうちに心が浄化されるようです。
さてチベット仏教への関心からBCAそしてSSが注目されるようになりましたが、日中では漢訳である『大乗集菩薩学論』の出来の悪さもあってかあまり注目されることはありませんでした。サンスクリット語原典からの直訳である本作を通し大乗仏教(とくに中観派)の精神・行を学びましょう。
2024/07/08