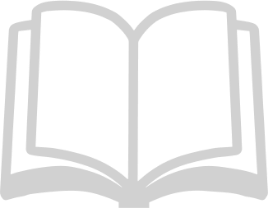大絶画さんの公開ページ レビュー一覧 2ページ
レビュー
鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』は『般若心経』の次ぎに日本で読まれたお経でしょう。しかし何度となく読み進めるとその内容や構成に違和感を覚えると思います。
本書は『妙法蓮華経』はもちろん他2種の漢訳、サンスクリット語原典はもちろんチベット語テキストなど各種テキストを比較して法華経の古層を明らかにしています。その過程で様々な経典をまとめ1つのテキストに構成されたことが明らかになります。
さて入門書とされる本書ですが、初心者向けに書かれているとはいえ上級者・研究者も満足できる内容になっています。既存の解説書では満足できない方におすすめです。
2024/04/28
『孟子』は儒教の聖典・四書の一つであり、孔子と並ぶ聖人・孟子の言行録です。『論語』とともに読んで損はありませんが『論語』ほど現代語訳や解説書が充実していないのも事実です。
本書は集英社「全釈漢文大系」を底本としており訳者も日本を代表する中国哲学者であった宇野氏で現代語訳も確かです。構成は章ごとに書き下し文・現代語訳と続き、原文は章末に返り点付きでまとめて掲載されています。
(おそらく分冊にしないための工夫なのでしょうが)訳注がないのが気になりますが、一巻本で気軽に読めますし『孟子』を手に取ろうという方におすすめです。また同文庫には吉田松陰による解説『講孟箚記』も収録されていますので、合せて読むといいでしょう。
2024/04/16
『孟子』は儒教の聖典・四書の一つであり、孔子と並ぶ聖人・孟子の言行録です。『論語』とともに読んで損はありませんが『論語』ほど現代語訳や解説書が充実していないのも事実です。
本書は集英社「全釈漢文大系」を底本としており訳者も日本を代表する中国哲学者であった宇野氏で現代語訳も確かです。構成は章ごとに書き下し文・現代語訳と続き、原文は章末に返り点付きでまとめて掲載されています。
(おそらく分冊にしないための工夫なのでしょうが)訳注がないのが気になりますが、一巻本で気軽に読めますし『孟子』を手に取ろうという方におすすめです。また同文庫には吉田松陰による解説『講孟箚記』も収録されていますので、合せて読むといいでしょう。
2024/04/16
日本で「浄土」といえば阿弥陀如来の西方浄土を思い浮かべる方がほとんどだろう。しかしかつては弥勒菩薩の上生・下生思想(釈迦入滅後、56億7千万年後に弥勒が下天する)から生まれた弥勒の浄土信仰が存在した。
本書ではインドで発生し中国・朝鮮から日本に弥勒信仰が伝わったか、いかなる変遷を経て、法然・親鸞の阿弥陀信仰に取って代わられたかが手堅くまとめられている。
現代の信仰についてはまとめられていないが、その点は著者も述べるように宮田登著『ミロク信仰の研究』などでカバーできる。
厭離穢土(現世否定)とは異なる現世肯定を説いた弥勒信仰の魅力を堪能してほしい。
2024/02/26
日本で「浄土」といえば阿弥陀如来の西方浄土を思い浮かべる方がほとんどだろう。しかしかつては弥勒菩薩の上生・下生思想(釈迦入滅後、56億7千万年後に弥勒が下天する)から生まれた弥勒の浄土信仰が存在した。
本書ではインドで発生し中国・朝鮮から日本に弥勒信仰が伝わったか、いかなる変遷を経て、法然・親鸞の阿弥陀信仰に取って代わられたかが手堅くまとめられている。
現代の信仰についてはまとめられていないが、その点は著者も述べるように宮田登著『ミロク信仰の研究』などでカバーできる。
厭離穢土(現世否定)とは異なる現世肯定を説いた弥勒信仰の魅力を堪能してほしい。
2024/02/26
昨年(2023年)は10年に一度あるいは100年の一度の不祥事が次々と明らかになりました。
このような企業の不祥事が起こる度、成員の知識や権限が問題にされます。いわく「マニュアルが徹底されていなかった」「監査部門の機能していなかった」などです。そして「コンプライアンス教育を徹底する」「監査部門を強化する」など対策が行われます。しかしそのようなことで防止はできるのか。
そしてニーバーは個人は自分と同じように相手を理解できないし配慮もできない。また組織の強制力(権力)は個人の良心を容易く凌駕する。さらに指導者の良心が成員に暴力的に働くことがあると明らかにします。
ニーバーの分析に容赦はありません。しかし改善する努力そのものは評価しています。
ニーバーが1960年の序文でいうように本作には古くなった部分が多々あります。しかしその分析は古びておらず、もしかしたら個人と社会の相剋はいっそう強くなっているかもしれません。いま一度ニーバーの言葉に耳を傾けましょう。
2024/02/25
昨年(2023年)は10年に一度あるいは100年の一度の不祥事が次々と明らかになりました。
このような企業の不祥事が起こる度、成員の知識や権限が問題にされます。いわく「マニュアルが徹底されていなかった」「監査部門の機能していなかった」などです。そして「コンプライアンス教育を徹底する」「監査部門を強化する」など対策が行われます。しかしそのようなことで防止はできるのか。
そしてニーバーは個人は自分と同じように相手を理解できないし配慮もできない。また組織の強制力(権力)は個人の良心を容易く凌駕する。さらに指導者の良心が成員に暴力的に働くことがあると明らかにします。
ニーバーの分析に容赦はありません。しかし改善する努力そのものは評価しています。
ニーバーが1960年の序文でいうように本作には古くなった部分が多々あります。しかしその分析は古びておらず、もしかしたら個人と社会の相剋はいっそう強くなっているかもしれません。いま一度ニーバーの言葉に耳を傾けましょう。
2024/02/25
イスラームの影響は日に日に強くなっていますから「コーランを読みたい」と考える方は多いでしょうね。
アラビア語との対訳も出ていますが、日本語で読みたければ岩波文庫の井筒訳をおすすめします。とくに井筒氏は『「コーラン」を読む』という最良の副読本を著わしていますから日本人にもイスラーム文化を理解できるはずです。
2024/01/21
ある文化を理解する上で、その聖典を読むことが重要である。とくにイスラーム文化圏の影響は日に日に強くなっていますから「『コーラン』を読みたい」と考える方は多いでしょう。しかし著者がいうように日本人にとって時間的・空間的に離れた『コーラン(クルアーン)』を理解することは無理があります。
著者は岩波文庫版『コーラン』の日本語訳を手がけ、祈祷文であり序章「開扉」の章を10回のセミナーで解釈学的思考を用いて読み解く様は圧巻の一言です。
井筒氏以後も『コーラン』の日本語訳・解説は存在しますが、氏ほど読み込んだ方はいないかもしれません。本書を通し『コーラン』の扉を開きましょう。
2024/01/17
ある文化を理解する上で、その聖典を読むことが重要である。とくにイスラーム文化圏の影響は日に日に強くなっていますから「『コーラン』を読みたい」と考える方は多いでしょう。しかし著者がいうように日本人にとって時間的・空間的に離れた『コーラン(クルアーン)』を理解することは無理があります。
著者は岩波文庫版『コーラン』の日本語訳を手がけ、祈祷文であり序章「開扉」の章を10回のセミナーで解釈学的思考を用いて読み解く様は圧巻の一言です。
井筒氏以後も『コーラン』の日本語訳・解説は存在しますが、氏ほど読み込んだ方はいないかもしれません。本書を通し『コーラン』の扉を開きましょう。
2024/01/17
本講話は一般的に「ドイツ国民に告ぐ」で知られています。
ナポレオン率いるフランス軍の監視の下、講話は開かれました。フィヒテ自身死も覚悟していたといいます。
さて内容はいたずらにナショナリズムを煽るのではなく、あくまでも人間の理性・良心に訴えました。出版の自由、言語教育、それらを統括する国家のあり方など普遍性・先見性が見えます。
当時から理想主義的な国家論に批判があったようですが、フィヒテが訴えるように激動の時代に必要なのは何よりも自律的な人材です。現在の日本は占領下ではありませんが、不安定な世界情勢、そして2024年の能登半島地震と混迷の中にいます。いま一度フィヒテの声に耳を傾ける時なのかもしれません。
2024/01/08
本講話は一般的に「ドイツ国民に告ぐ」で知られています。
ナポレオン率いるフランス軍の監視の下、講話は開かれました。フィヒテ自身死も覚悟していたといいます。
さて内容はいたずらにナショナリズムを煽るのではなく、あくまでも人間の理性・良心に訴えました。出版の自由、言語教育、それらを統括する国家のあり方など普遍性・先見性が見えます。
当時から理想主義的な国家論に批判があったようですが、フィヒテが訴えるように激動の時代に必要なのは何よりも自律的な人材です。現在の日本は占領下ではありませんが、不安定な世界情勢、そして2024年の能登半島地震と混迷の中にいます。いま一度フィヒテの声に耳を傾ける時なのかもしれません。
2024/01/08
ダンテの『神曲』はキリスト教文学の最高峰されます。河出文庫には平川訳が収録されていますから挑戦された方も多いでしょう。
ただ訳注が充実した平川訳でも日本人に『神曲』は取っ付きにくいと思います。本書は40年以上『神曲』に向き合った著者による講義であり最良の副読本です。
キリスト教文学の枠組を超えイタリア文学そして比較文学の面白さが堪能できます。『神曲』の予習にあるいは復習に。
2024/01/04
小乗と大乗を分けるのが菩提心(利他心、求道心)、そして顕教と密教を分けるのは究極の菩提心の有無になるでしょう。
本書は龍樹作とされる『菩提心の解説』をダライ・ラマ猊下が解説されています。
さて本書で説かれる究極の菩提心とは微細な意識のレベルで見た菩提心ということになるでしょう。これは龍樹の中観の実戦ともいえます。
最後に究極の菩提心は猊下ですら達していないといいます。我々、凡夫では想像すらできない境地です。しかし弛まず精進することに意味があります。『菩提心の解説』を通して究極の慈悲が見えるはずです。
2023/12/28
『キリストにならいて』の翻訳はいくつ存在します。自分の所属する宗派や書店などで手に取って選ぶのが一番とは思いますが、あえて薦めるなら教文館の由木訳です。
訳者の学識はもちろんですが、氏の信仰が本作が持つ霊性を引き出していると思います。
私はキリスト教徒ではありませんが、読み返す度本書が持つ情熱・克己心に身が引き締まる思いがします。自己修養にお勧めです。
2023/12/26
本作は大衆論の古典です。
初版は1951年ですが、大衆運動の担い手たちの分析は古びていません。それは中山氏の新訳でいっそうはっきりしたでしょう。
さて大衆運動は何度となく社会を動かしてきました。それは歴史が証明しています。しかしそれは肯定的な成果だけではありません。ホッファー自身、それを理解しており、いかに運動を健全なものにするか、それが本書の狙いです。
ひるがえって現代のSNS上など様々なムーブメント(運動)が起きています。それが炎上に発展することもあります。私たちは余計な火の粉を被らないためにホッファーの分析に耳を傾けましょう。
2023/12/22
インドの破壊神シヴァの息子ガネーシャは日本では聖天または歓喜天と呼ばれます。
像頭の造形が目立ちますが、中には女尊と一対になった双身像が存在します。これは聖天の破壊的な力を女人になった十一面観音が抑えているという構造で多くの寺院で秘仏となっているようです、
そしてこういった双身像のモデルは男女一対になったミトゥナが元になっておりアジアの各地で見られます。それはヒンドゥー教のシャクティ信仰を反映したもので、人間の欲望とくに性欲の昇華です。
ただこういった背景があるためか秘仏になっているため著者といえど歓喜天信仰には不明な点があるようです。とはいえ本書を通し歓喜天信仰の奥深さ、人間の生命(欲望)の讃歌と一筋縄ではいかない歓喜天のご利益・哲学が理解できるはずです。
2023/12/18
インドの破壊神シヴァの息子ガネーシャは日本では聖天または歓喜天と呼ばれます。
像頭の造形が目立ちますが、中には女尊と一対になった双身像が存在します。これは聖天の破壊的な力を女人になった十一面観音が抑えているという構造で多くの寺院で秘仏となっているようです、
そしてこういった双身像のモデルは男女一対になったミトゥナが元になっておりアジアの各地で見られます。それはヒンドゥー教のシャクティ信仰を反映したもので、人間の欲望とくに性欲の昇華です。
ただこういった背景があるためか秘仏になっているため著者といえど歓喜天信仰には不明な点があるようです。とはいえ本書を通し歓喜天信仰の奥深さ、人間の生命(欲望)の讃歌と一筋縄ではいかない歓喜天のご利益・哲学が理解できるはずです。
2023/12/18
空海は主著『十住心論』は人間の十段階に分け、その最終段階を密教的な世界と位置づけました。そして『秘蔵宝鑰』はその要約版です。
空海の理論はヘーゲルの『精神の現象学』のように人間精神の発展を描いていますが、より複雑で重層的です。またすべての仏教そして非仏教を包括しています。著者も指摘していますが、こういった全人的な思想がおよそ1200年前に存在していたことに驚きを隠せません。空海は仏教のみならず日本文化に多大な影響を与えましたが、当然の結果といえるでしょう。
本書を片手に『秘蔵宝鑰』に挑戦して下さい。そこにあなたが望むすべてがあります。
2023/12/17
空海は主著『十住心論』は人間の十段階に分け、その最終段階を密教的な世界と位置づけました。そして『秘蔵宝鑰』はその要約版です。
空海の理論はヘーゲルの『精神の現象学』のように人間精神の発展を描いていますが、より複雑で重層的です。またすべての仏教そして非仏教を包括しています。著者も指摘していますが、こういった全人的な思想がおよそ1200年前に存在していたことに驚きを隠せません。空海は仏教のみならず日本文化に多大な影響を与えましたが、当然の結果といえるでしょう。
本書を片手に『秘蔵宝鑰』に挑戦して下さい。そこにあなたが望むすべてがあります。
2023/12/17
『法句経(ダンマパダ、真理のことば)』は仏教の古層に位置する聖典で、簡潔で滋味に富んだ内容は欧米で「東方の聖書」と賞賛されました。
本書では古代インドの経済・政治的背景を解説しつつ『法句経』の普遍的な精神を述べています。
現代は情報過多な時代で多くの邪見に満ちています。邪見に陥らず澄んだ心で時代を見据えるためにインド・中国そして日本と伝わった『法句経』の精神に立ち帰るべきなのかもしれません。
2023/12/17
第4巻「実践篇」のレビューです。
内容は空海の師・恵果から口伝されたとされる『秘蔵記』、真言行者の戒(心構え)を説いた『三昧耶戒序』ほか、日本人による初のサンスクリット語解説であろう『梵字悉曇字母并釈義』と在家・一般向けというよりは出家・行者向けといまえす。
とはいえどの作品も「真言行者は他者のために行動せよ」と利他・慈悲の精神を謳っており一般読者にも得るものが大きいでしょう。
2023/12/11
大法輪閣版のレビューです。
『安心決定鈔』は蓮如が「40年以上読んでも読み飽きない」「まるで黄金を掘り起こすような聖教(聖典)」と絶賛していますが、その由来はよくわかっていません。著者はおそらく浄土宗西山派の人間だろうといわれています。
本来、浄土真宗とは関係のない聖教をなぜ蓮如は重要視したのか。あるいは真宗に欠けた要素を求めたのか、それは読者に委ねます。
さて由来はどうあれ、本書には漫然と生きる我々に訴えかけるものがあります。それは機(私たち)と法(阿弥陀如来)が一体であり、つねに死を意識し阿弥陀仏にすがるよう説いています。
現代において「死」は遠のいたように思えます。しかし数年前のコロナ感染症、国外に目を向ければ戦争・テロと「死」がすぐ側まで近くにあることが実感できます。浄土宗・真宗の教徒でなくとも読んでいただきたいです。
2023/12/09
大法輪閣版のレビューです。
『安心決定鈔』は蓮如が「40年以上読んでも読み飽きない」「まるで黄金を掘り起こすような聖教(聖典)」と絶賛していますが、その由来はよくわかっていません。著者はおそらく浄土宗西山派の人間だろうといわれています。
本来、浄土真宗とは関係のない聖教をなぜ蓮如は重要視したのか。あるいは真宗に欠けた要素を求めたのか、それは読者に委ねます。
さて由来はどうあれ、本書には漫然と生きる我々に訴えかけるものがあります。それは機(私たち)と法(阿弥陀如来)が一体であり、つねに死を意識し阿弥陀仏にすがるよう説いています。
現代において「死」は遠のいたように思えます。しかし数年前のコロナ感染症、国外に目を向ければ戦争・テロと「死」がすぐ側まで近くにあることが実感できます。浄土宗・真宗の教徒でなくとも読んでいただきたいです。
2023/12/09
蓮如をはじめ門人たちの言行録です。原文、現代語訳・解説という流れになっており古文を読み慣れていない方にも取っ付きやすくなっています。
さて読み進めていく中で気付くのは蓮如が「信心」を重要視していることです。「浄土真宗は念仏だけ唱えればいいのではないのか」と疑問を持つ方もいるでしょうが、蓮如自身、信心から念仏が生まれさらに信心を強くすると考えていたようです。とくに門弟たちにいたずらに他宗派を攻撃しないよう呼びかけていたことも印象的です。これは真宗や浄土宗が「本願ぼこり(念仏を唱えれば悪事をしても許される考える人)」への対処に苦労してきたことと無関係ではないでしょう。
私は他宗派ではありますが、蓮如の態度には学ぶべき点が多々ありました。
2023/12/05
蓮如をはじめ門人たちの言行録です。原文、現代語訳・解説という流れになっており古文を読み慣れていない方にも取っ付きやすくなっています。
さて読み進めていく中で気付くのは蓮如が「信心」を重要視していることです。「浄土真宗は念仏だけ唱えればいいのではないのか」と疑問を持つ方もいるでしょうが、蓮如自身、信心から念仏が生まれさらに信心を強くすると考えていたようです。とくに門弟たちにいたずらに他宗派を攻撃しないよう呼びかけていたことも印象的です。これは真宗や浄土宗が「本願ぼこり(念仏を唱えれば悪事をしても許される考える人)」への対処に苦労してきたことと無関係ではないでしょう。
私は他宗派ではありますが、蓮如の態度には学ぶべき点が多々ありました。
2023/12/05
現在、法藏館文庫に収録されておりますので文庫版のレビューです。訳文を見直したそうなので小さな文字が苦でない方はそちらがいいでしょう。
中国の僧であった義浄によるインド僧生活記録です。
食事や着物、トイレの作法など仔細に記録されています。
たびたび中国仏教(とくに道宣ら律宗)への批判が挟まれることから、彼が釈迦の正則(正しい規則)を求めていたことがうかがえます。それは「根本説一切有部律(根本有部律)」の翻訳にも生かされたことでしょう。
さて仏教は「戒・定・慧」の三学兼修と謳っていますが、「戒(律)」は軽視される傾向にあります。それは「根本有部律」翻訳後も変わらなかったようです。
仏教の実践を行う上で「戒律」の問題は避けられません。とくに日本仏教は戒律の研究が不足しているといわれ、いま一度義浄の言葉に耳を傾ける時なのかもしれません。
2023/11/26
現在、法藏館文庫に収録されておりますので文庫版のレビューです。訳文を見直したそうなので小さな文字が苦でない方はそちらがいいでしょう。
中国の僧であった義浄によるインド僧生活記録です。
食事や着物、トイレの作法など仔細に記録されています。
たびたび中国仏教(とくに道宣ら律宗)への批判が挟まれることから、彼が釈迦の正則(正しい規則)を求めていたことがうかがえます。それは「根本説一切有部律(根本有部律)」の翻訳にも生かされたことでしょう。
さて仏教は「戒・定・慧」の三学兼修と謳っていますが、「戒(律)」は軽視される傾向にあります。それは「根本有部律」翻訳後も変わらなかったようです。
仏教の実践を行う上で「戒律」の問題は避けられません。とくに日本仏教は戒律の研究が不足しているといわれ、いま一度義浄の言葉に耳を傾ける時なのかもしれません。
2023/11/26
『入菩薩行論』の名が表わすように本作では菩薩の実践を説いています。
それは徹底的な利他の精神に貫かれており、読者は尻込みしてしまうかもしれません。しかし弛むまず、そして完璧に実践できなかったとしても諸仏に懺悔することで確実に菩薩の階段を昇ることができるはずです。
内容も(中観帰謬論証派を解説した9章を除けば)非専門家でも理解できるはずです。
本書をお供に菩薩の道へと入りましょう。
2023/11/17
「東洋は西洋に比べ合理的思考が発達しなかった」といわれます。一面では正しいものの「東洋論理学は取るに足らない」と考えるのは誤りです。
ウィトゲンシュタイン研究で知られる著者は合理的思考を古典記号論理学と弁証法と定義し、インド論理学とくに仏教論理学(因明)、そして天台教学や華厳経学、儒教、墨家、老荘思想、易経と論じていきます。
その過程で西洋論理学にも負けない論理体系が構築されたことが明らかになりますが、同時に高度で抽象的な論理が構築できなかった理由も明らかになります。
しかし現実において西洋合理思想にも限界は見えています。西洋の円志向に代る楕円志向とは何か。ご確認下さい。
2023/11/11
「東洋は西洋に比べ合理的思考が発達しなかった」といわれます。一面では正しいものの「東洋論理学は取るに足らない」と考えるのは誤りです。
ウィトゲンシュタイン研究で知られる著者は合理的思考を古典記号論理学と弁証法と定義し、インド論理学とくに仏教論理学(因明)、そして天台教学や華厳経学、儒教、墨家、老荘思想、易経と論じていきます。
その過程で西洋論理学にも負けない論理体系が構築されたことが明らかになりますが、同時に高度で抽象的な論理が構築できなかった理由も明らかになります。
しかし現実において西洋合理思想にも限界は見えています。西洋の円志向に代る楕円志向とは何か。ご確認下さい。
2023/11/11
一般に「東洋人は西洋人に比べ合理的な思考が不得意だ」といわれます。しかし『ミリンダ王の問い』において僧侶ナーガセーナはミリンダ王は堂々と議論を行いました。これはインドにおいて多くの知識人(沙門)たちが議論をくり返し技術を磨いたことと無関係ではないでしょう。
前半部ではインドの討論のルールが記されており、現在でも納得できる点があります。と同時にインドでは目的志向の論理学であったためか、西洋ほど高度な記号論理学は発展しなかったといえるかもしれません。
最後によく「日本人は議論が下手だ」といわれます。場合によっては「日本語は非合理的な言語だから」と筋違いな指摘がなされます。
しかし先人たちが否定してきたように日本語はけっして非合理的な言語ではありませんし、単純に相手(主に欧米)のやり方を知らない、そして何よりも議論に慣れていないことが大きいでしょう。およそ1800年前にミランダ王と討論したナーガセーナのように我々自身インドの論理学そして問答法を学ぶべきと考えます。
2023/11/09
一般に「東洋人は西洋人に比べ合理的な思考が不得意だ」といわれます。しかし『ミリンダ王の問い』において僧侶ナーガセーナはミリンダ王は堂々と議論を行いました。これはインドにおいて多くの知識人(沙門)たちが議論をくり返し技術を磨いたことと無関係ではないでしょう。
前半部ではインドの討論のルールが記されており、現在でも納得できる点があります。と同時にインドでは目的志向の論理学であったためか、西洋ほど高度な記号論理学は発展しなかったといえるかもしれません。
最後によく「日本人は議論が下手だ」といわれます。場合によっては「日本語は非合理的な言語だから」と筋違いな指摘がなされます。
しかし先人たちが否定してきたように日本語はけっして非合理的な言語ではありませんし、単純に相手(主に欧米)のやり方を知らない、そして何よりも議論に慣れていないことが大きいでしょう。およそ1800年前にミランダ王と討論したナーガセーナのように我々自身インドの論理学そして問答法を学ぶべきと考えます。
2023/11/09
「日本を代表する女神は誰か」と問われたら弁財天と答える方は多いのではないでしょうか。
弁財天の源流をたどるとインド神話のサラスヴァティーに行き着きます。漢訳では弁才天とされ、とくに福の神であることを強調する場合「弁財天」と表記されます。
水の神であり音楽の神であるサラスヴァティーがいかに福の神・弁財天として日本の風土に受け容れらたのか、豊富な資料や図絵から理解できます。
2023/11/04
大乗仏教は大乗(大きな乗り物)というように誰もが仏陀(覚者)になれると説きます。その根拠はすべてのものは仏陀になる可能性(仏性)を持つという“如来蔵”思想です。
本書に収録されている『如来蔵経』『不増不減経』『勝鬘経』(如来蔵三部経)以外は華厳、宝積、経集と出典も様々ですが、多くの比喩を用いて「如来蔵」を説明しようとしています。
研究者の中には如来蔵をアートマン思想の残滓と見る方もしますが、大乗が多くの信徒に開かれた点は否定できません。
般若経典が説く「空」とともに大乗仏教の二大支柱でありぜひ学びましょう。
2023/11/03
本書に収録されている二経は大乗仏教初期に成立したと考えられます。そのためか部派(小乗)仏教とは異なった論理が展開され、十大弟子をはじめとする門弟たちが論破される様は痛快ですらあります。
二経はどちらもチベット語訳からの重訳ですが(『維摩経』サンスクリット語原典が発見されたのは1999年)チベット語テキストが逐語訳であり長尾氏をはじめ翻訳者が学識が確かで格調高く読みやすい訳になっています。
『維摩経』はとくに構成が素晴らしいだけでなく大乗仏教の理念が見事に描かれており『法華経』とともに仏教文学の頂点といえます。大乗仏教の入口に相応しいでしょう。
2023/11/03
本書に収録されている二経は大乗仏教初期に成立したと考えられます。そのためか部派(小乗)仏教とは異なった論理が展開され、十大弟子をはじめとする門弟たちが論破される様は痛快ですらあります。
二経はどちらもチベット語訳からの重訳ですが(『維摩経』サンスクリット語原典が発見されたのは1999年)チベット語テキストが逐語訳であり長尾氏をはじめ翻訳者が学識が確かで格調高く読みやすい訳になっています。
『維摩経』はとくに構成が素晴らしいだけでなく大乗仏教の理念が見事に描かれており『法華経』とともに仏教文学の頂点といえます。大乗仏教の入口に相応しいでしょう。
2023/11/03
多くの宗派では「戒・定・慧」の三学を修めることが求められます。この場合の「戒」とは信徒の心構え(マナー、エチケット)といった意味です。また戒を定めることで信徒の指針が定まります。
さて部派(小乗)仏教から大乗仏教に移る過程でこれまでの自利的な戒から利他的な戒が必要になりました。その利他的な戒=菩薩戒として本経『梵網経』に説かれる十重四十八軽戒が利用されるようになりました。
菩薩戒を意識することで菩薩の生活がスタートするといえます。
本書は下巻・菩薩戒の原文・現代語訳、成り立ち、解説も充実しており在家にも理解しやすくなっています。『梵網経』は中国撰述の偽経とされますが、その内容は世界に誇れるものです。あなたも菩薩の入口に足を進めましょう。
2023/10/28
多くの宗派では「戒・定・慧」の三学を修めることが求められます。この場合の「戒」とは信徒の心構え(マナー、エチケット)といった意味です。また戒を定めることで信徒の指針が定まります。
さて部派(小乗)仏教から大乗仏教に移る過程でこれまでの自利的な戒から利他的な戒が必要になりました。その利他的な戒=菩薩戒として本経『梵網経』に説かれる十重四十八軽戒が利用されるようになりました。
菩薩戒を意識することで菩薩の生活がスタートするといえます。
本書は下巻・菩薩戒の原文・現代語訳、成り立ち、解説も充実しており在家にも理解しやすくなっています。『梵網経』は中国撰述の偽経とされますが、その内容は世界に誇れるものです。あなたも菩薩の入口に足を進めましょう。
2023/10/28
「基本聖典」とあるように日常で必要な経典がほぼ収録されています。在家それに出家を目指している方におすすめです。
ただあくまで経典のみなので注釈は最小限で、内容は簡潔・明快ですが本書だけで解脱を目指すのは難しいと思います。
とはいえこれだけ必要十分にテーラワーダ(上座部)仏教に触れられる書籍は希有ですので、日々の行いの反省にご活用下さい。
2023/10/22
本作は儒教・道教・仏教を比較した作品で、空海の自伝的小説であります。
若き空海がいかに三教を学ぶ過程で仏教の優位性を見出し大宗教家となったか。後年の『十住心論』や『秘蔵宝鑰』に通じる思想が展開されます。
現代語訳も丁寧で、原文(書き下し文)も乗っておりますので空海の思想を学びたいという方におすすめです。
2023/10/17
「密教とは何か?」この問いに「密教とは仏教の一部分(一宗派)」と答えることもできるし「密教とはすべての仏教を包括する教え」と考えることもできます。
さて歴史上、2つの見方を明らかにしたのは空海です。現代でもダライ・ラマ猊下が「密教の指導者として上座部・顕教も学ぶ必要がある」とおっしゃっています。
本書では包括的な視点から密教の成り立ち、そして未来への展望が描かれています。こういった視点を学ぶことでグローバルといいつつ汲々としている世界情勢を救う手立てが見つかるのではないかと考えます。
2023/10/13