1 票
| 著者 | 高橋和巳 |
|---|---|
| 出版社 | 旺文社文庫 |
| ジャンル | 文芸書 |
| 登録日 | 2013/03/06 |
| リクエストNo. | 57347 |
リクエスト内容
1931年に生まれ1971年に死去した中国文学者が、大学の代表者として学園紛争の矢面に立ちつつ、「若い未知の友」に向けてつづったエッセイ集。戦中の少年が戦後の世代・社会に対して感じ、思考した内容は、21世紀の日本がなぜこのように立っているのかを理解する上で示唆に富むものであり、現在起きている、また、これからも続いていく社会変革の「似かよった事例」として、読み継がれるべきものである。
以下、「隔絶の時代」より抽出。
「(略)こんなにまでして能率を上げねばならないか。(略)私の感じた寒気は(略)人間存在に対するに十世紀的解釈へのあり方への戦慄のようなものだった。言ってみれば、<群れ>はあるのだが、それは人間の集団ではなかったのである。(略)同じ状況は生活の全域にゆきわたりつつあって、自由さ、豊かさ、便利さといった飴玉をしゃぶりながら、人は現実から、経験から、経験交流からすらひきはなされていっている。」
投票コメント
全1件
-
1981年の大学入試の問題文として出され感動した。時代・社会・科学技術の変化を越える深い示唆に富む本書を現代の若者に読んでもらいたい。GOOD!1
・自立的思弁を育てるにはどうすればよいのかと考えてみますと(略)いろんな事実をイメージをともなうかたちで数多く知ることなのです。(略)逸話の形で、人間のいろんな行為の類型を覚えこむのが上手なやり方だと思います。(略)平和にも、平和の理論だけではなく、人の心を打つ平和のイメージが必要なのです。(イメージをはぐくむ)
・読むことと書き述べることの比率が、時間的に八対二ぐらいであるのが一番精神に健康であるような気がする。(略)魚が網にかかるのは網目の一つにすぎないが(略)たまたま役立つ網目の背後に広大な無駄の部分が必要なのであって、あまりカード式に整理されすぎた精神はかえって不毛となるだろう。(精神の網)
・(略)まだ新しい読書の態度が確立していないということは、(略)何か予期しない<読書>の在り方が、生まれないとも限らない。二十世紀後半から二十一世紀にかけて、独自な文化が形成されるのは、おそらく、それからのことであろう。(未だ形なき新しい読書) (2013/03/06)
読後レビュー
NEWS
-
2013/03/06
『現代の青春』(高橋和巳)の復刊リクエスト受付を開始しました。
復刊実現の投票はあなたの投票から。
復刊リクエスト投票であなたの思いを形にしましょう!


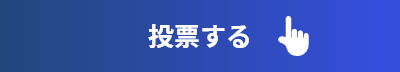



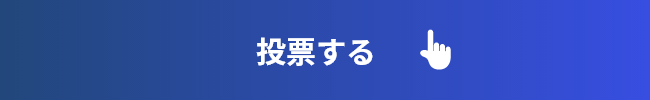
kakiko