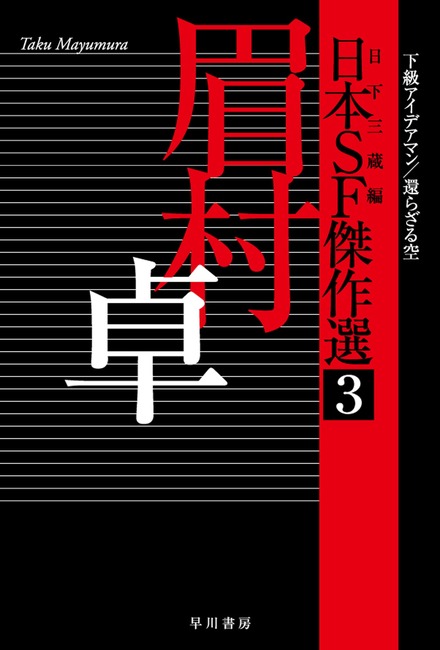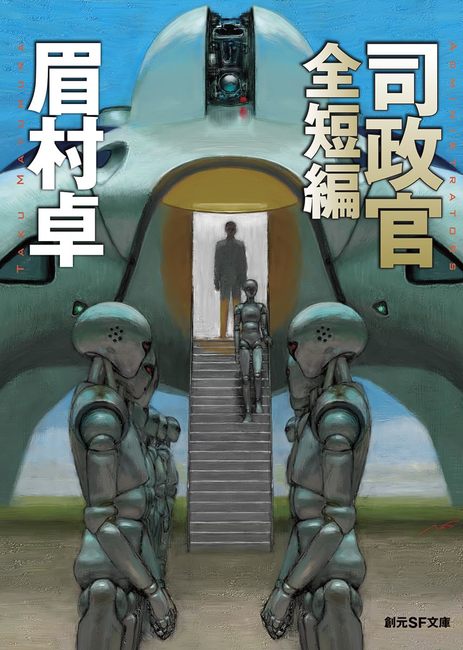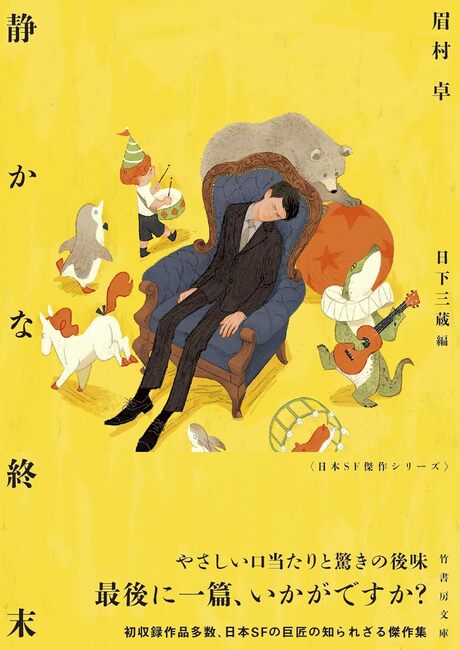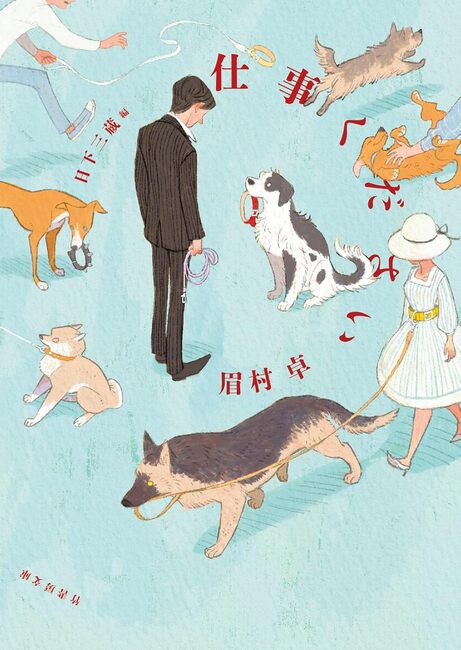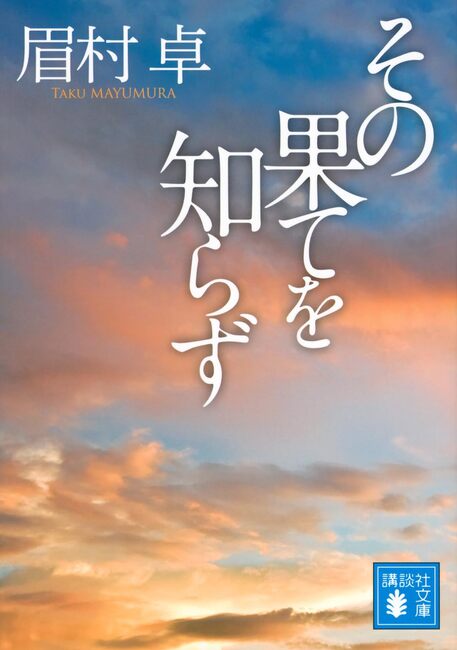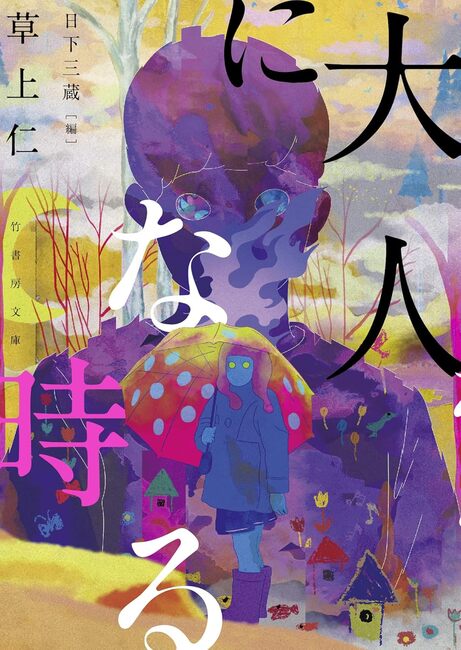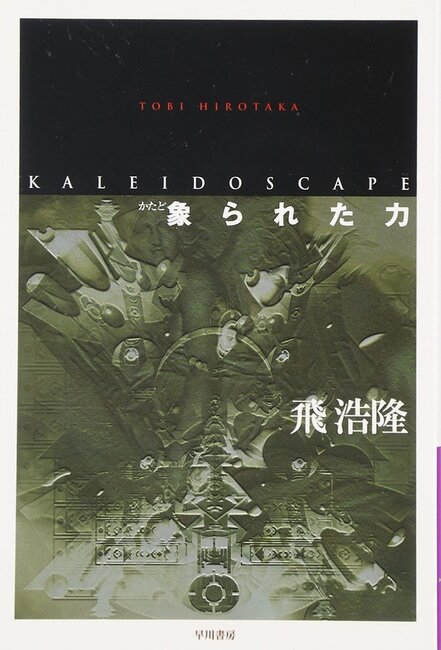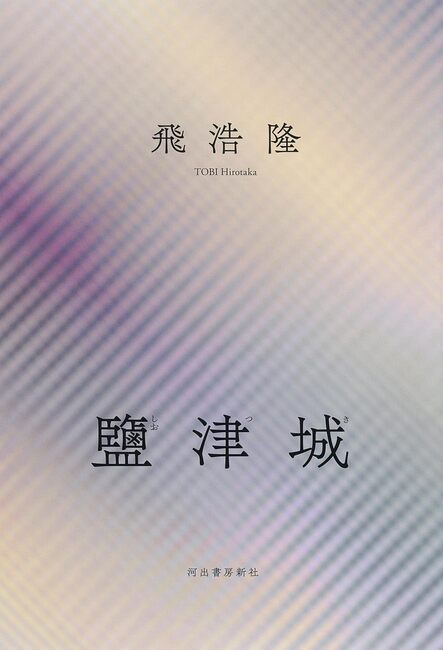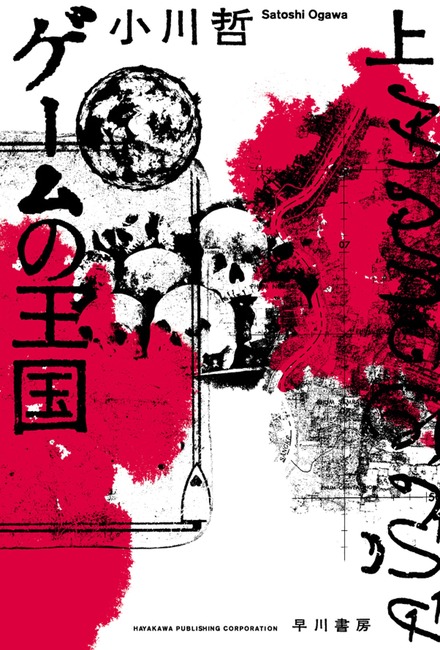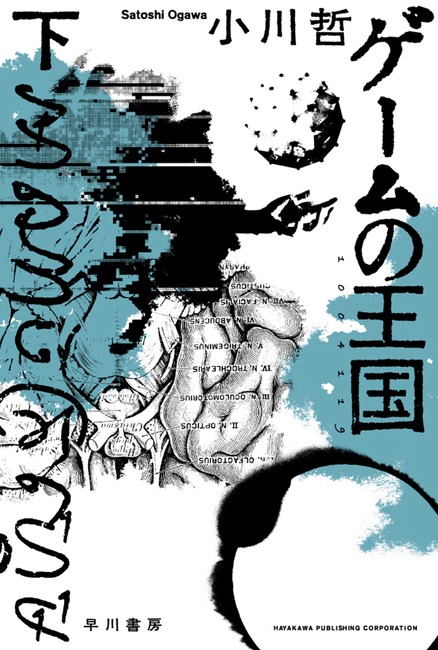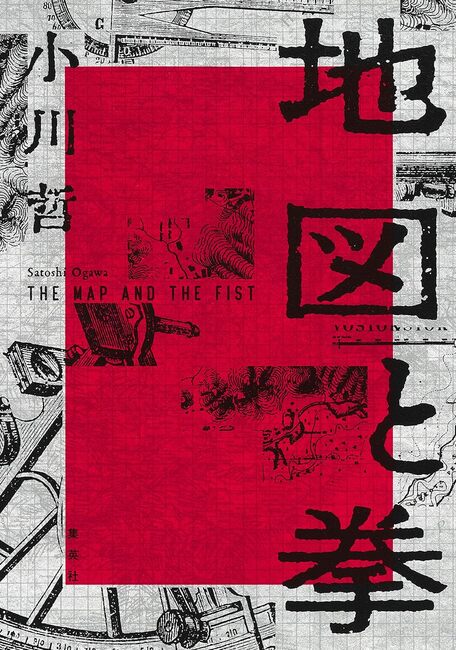日下三蔵セレクト SFフェア 第6回
日下三蔵セレクト SFフェア 第6回

眉村卓は日本SF第一世代を代表する作家の一人である。『なぞの転校生』や『ねらわれた学園』といったジュブナイル作品は、何度もドラマ化、アニメ化されているので、多くの人に知られているだろう。
一般向けの作品にも、幅広い傾向のものがあるが、初期から一貫して書き続けていたのが、宇宙もの・未来ものである。小学館のP+D BOOKSから、宇宙ものの長篇『燃える傾斜』と未来ものの長篇『EXPO'87』が復刊されているので、ぜひ読んでいただきたい。
一般向けの作品にも、幅広い傾向のものがあるが、初期から一貫して書き続けていたのが、宇宙もの・未来ものである。小学館のP+D BOOKSから、宇宙ものの長篇『燃える傾斜』と未来ものの長篇『EXPO'87』が復刊されているので、ぜひ読んでいただきたい。
- 本体価格:1,500 円(税込円)
- 本体価格:1,700 円(税込円)
- 本体価格:1,300 円(税込円)
- 本体価格:1,300 円(税込円)
- 本体価格:800 円(税込円)
- 本体価格:1,400 円(税込円)
- 本体価格:1,400 円(税込円)
- 本体価格:780 円(税込円)
- 本体価格:2,000 円(税込円)
- 本体価格:840 円(税込円)
- 本体価格:2,200 円(税込円)
眉村卓 著 / 日下三蔵 編
短篇の代表作については、ハヤカワ文庫《日本SF傑作選》第3巻の眉村卓集に、単行本初収録作品二篇を含む二十二篇をまとめておいた。筒井康隆が「眉村卓には変てこな宇宙生命体を考え出す才能があった」と評したように、「正接曲線」「わがパキーネ」「時間と泥」など、奇妙な生態を持った宇宙生物の登場する一連の作品はたいへん面白い。
第一部には、宇宙生物ものを中心とした短篇集『重力地獄』の十一篇を丸ごと収め、井上雅彦編のオリジナル・アンソロジー《異形コレクション》に発表された未刊行の近作二篇を加えた。第二部には、「還らざる空」「準B級市民」「産業士官候補生」など、未来ものの傑作九篇を収録。全著作リストを含めて八百ページ近いボリュームになってしまったが、その分、読みごたえ充分の傑作選と自負しています。
第一部には、宇宙生物ものを中心とした短篇集『重力地獄』の十一篇を丸ごと収め、井上雅彦編のオリジナル・アンソロジー《異形コレクション》に発表された未刊行の近作二篇を加えた。第二部には、「還らざる空」「準B級市民」「産業士官候補生」など、未来ものの傑作九篇を収録。全著作リストを含めて八百ページ近いボリュームになってしまったが、その分、読みごたえ充分の傑作選と自負しています。
眉村卓
組織と人間の関係を描き続けた眉村卓の宇宙もの、未来ものは、やがて植民惑星を統治する司政官が、その星ならではのさまざまなトラブルに対処していく《司政官》シリーズへと発展。短篇集『司政官』『長い暁』、大長篇『消滅の光輪』『引き潮のとき』が書かれた。私の編集本ではないが、シリーズの短篇七作を作中年代順に配置した『司政官 全短編』の面白さは格別。ハヤカワ文庫の短篇集を気に入った方は、併せてどうぞ。
眉村卓 著 / 日下三蔵 編
眉村卓はショートショートの名手で、商業誌に発表した作品だけでも、千篇の星新一を上回る千三百篇以上がある。他に余命宣告された夫人のために、毎日書き続けたショ
ートショートは一七七八篇に達して、このエピソードは「僕と妻の1778の物語」として映画化もされた。つまり、作品数は三千篇を超えているのだ。
竹書房文庫の《日本SF傑作シリーズ》で編んだ『静かな終末』は、単行本に入って文庫化されなかった二十九篇、アンソロジーにのみ収録で個人短篇集に入っていない七篇、まったく単行本未収録の十四篇、合計五十篇を一挙に収めた。いずれもデビューから十年以内に発表された初期作品で、各社の文庫で既刊のショートショート集とは、ひとつも重なっていないレア作品集である。
ショートショート集とはいっても、三十枚近い短篇もいくつか含まれており、なかなか読みごたえのある一冊になっている。
竹書房文庫の《日本SF傑作シリーズ》で編んだ『静かな終末』は、単行本に入って文庫化されなかった二十九篇、アンソロジーにのみ収録で個人短篇集に入っていない七篇、まったく単行本未収録の十四篇、合計五十篇を一挙に収めた。いずれもデビューから十年以内に発表された初期作品で、各社の文庫で既刊のショートショート集とは、ひとつも重なっていないレア作品集である。
ショートショート集とはいっても、三十枚近い短篇もいくつか含まれており、なかなか読みごたえのある一冊になっている。
眉村卓 著 / 日下三蔵 編
《日本SF傑作シリーズ》からは、もう一冊、奇妙な味の作品を中心とした『仕事ください』も出した。ハヤカワ文庫と角川文庫で出ていた『奇妙な妻』の全篇に、同傾向の
一篇と、「宇宙塵」掲載の未収録作三篇を加えたもの。こちらもすべて初期の十年の間に発表されたものばかりで、『静かな終末』と『仕事ください』の二冊を読んでいただ
ければ、著者の多彩なストーリーテラーぶりが確認できるはずだ。
眉村卓
宇宙もの、未来ものと並んで大きな位置を占めるのが、主人公が別の世界に迷い込んでしまう一連の「異世界もの」で、2012年に代表的な作品を、出版芸術社から《眉村卓
コレクション 異世界篇》全3巻として、まとめたことがある。現在は品切れで電子書籍も出ていないが、図書館などで手に取ってもらえるとうれしい。
晩年まで書き継いだ異世界ものは、著者自身を投影した人物が主人公として起用されることが多く、眉村さんは「私小説」ならぬ「私ファンタジー」と名付けていた。亡く なる直前まで書き続けて完成した遺作『その果てを知らず』も、その系統の傑作である。SF同人誌に参加したデビュー以前の話なども織り込まれており、SFファンには興 味の尽きない一冊。
晩年まで書き継いだ異世界ものは、著者自身を投影した人物が主人公として起用されることが多く、眉村さんは「私小説」ならぬ「私ファンタジー」と名付けていた。亡く なる直前まで書き続けて完成した遺作『その果てを知らず』も、その系統の傑作である。SF同人誌に参加したデビュー以前の話なども織り込まれており、SFファンには興 味の尽きない一冊。
草上仁 著 / 日下三蔵 編
82年にデビューして質の高いSF短篇を書き続けている草上仁は、日本SF第四世代作家ということになるだろう。八〇年代から九〇年代にかけて、ハヤカワ文庫から十三
冊も出ていた短篇集は、すべて品切れとなっていたが、2019年に出た久々の作品集『5分間SF』がヒットし、続けて『7分間SF』も刊行された。
多くの人が草上SFの面白さを再確認したが、本になっていない短篇は、いつの間にか百篇を超えてしまっていた。竹書房文庫《日本SF傑作シリーズ》で私が編んだ『キ スギショウジ氏の生活と意見』は、早川書房以外の媒体、具体的には徳間書店の「SFアドベンチャー」と角川書店の「野性時代」に掲載された未刊行作品を、サルベージす る目的の短篇集であった。この本の解説で、私はこう書いた。
多くの人が草上SFの面白さを再確認したが、本になっていない短篇は、いつの間にか百篇を超えてしまっていた。竹書房文庫《日本SF傑作シリーズ》で私が編んだ『キ スギショウジ氏の生活と意見』は、早川書房以外の媒体、具体的には徳間書店の「SFアドベンチャー」と角川書店の「野性時代」に掲載された未刊行作品を、サルベージす る目的の短篇集であった。この本の解説で、私はこう書いた。
草上短篇の特徴としては、「アイデアの奇抜さ」「文章の読みやすさ」「バラエティの豊かさ」などが挙げられるが、これらは、つまり「クオリティの高さ」という最大の特徴の要因ということになる。タイプとしては、第四短篇集『無重力でも快適』の解説で星新一が名前を挙げているフレドリック・ブラウンに、もっとも近い。長篇も、短篇も、SFも、ミステリも、すべて面白いという点も、ブラウンと同じだ。
日本でいうなら、まさに星新一。あるいはSFマンガの藤子・F・不二雄や岡崎二郎を想起していただければ、草上作品のアベレージの高さをイメージしやすいのではないだろうか。
同書には、88年から92年にかけて発表された十八篇に書下しの新作一篇を収録したが、三十年前の作品も、その面白さは、まったく色褪せていなかった。質の高いSF短篇を楽しみたい、という方に、自信を持ってお勧めする次第です。
日本でいうなら、まさに星新一。あるいはSFマンガの藤子・F・不二雄や岡崎二郎を想起していただければ、草上作品のアベレージの高さをイメージしやすいのではないだろうか。
草上仁 著 / 日下三蔵 編
『キスギショウジ氏の生活と意見』の好評を受けて編んだ『大人になる時』は、「野性時代」掲載作の残り四篇、オリジナル・アンソロジーのために書かれた三篇、その他の
雑誌に発表された三篇、書下しの新作二篇をまとめたもの。こちらもSFをベースに、サスペンスあり、ファンタジーあり、ホラーありと、バラエティ豊かな傑作揃いである。
飛浩隆
草上仁と同じ82年にデビューした飛浩隆は、兼業作家のため、とにかく寡作だが、その代わり、書かれた作品は、どれもこれも面白いという、現代日本を代表するSF作家の一人である。
92年までの十年間で十作しか発表しておらず、その後は2002年まで作品ナシという徹底ぶり。2002年、打ち捨てられた仮想現実空間を舞台にした《廃園の天使》三部作の第一作『グラン・ヴァカンス』を刊行して、SFファンの度肝を抜いた。
続く作品集『象られた力』で、2005年の第二十六回日本SF大賞を受賞。さらに作品集『自生の夢』では2017年の第三十八回日本SF大賞を受賞。同じ作家が同賞を二回受賞したのは、飛浩隆が初めてであった。(飛さんの後に、酉島伝法、長谷敏司の両氏が受賞している)
92年までの十年間で十作しか発表しておらず、その後は2002年まで作品ナシという徹底ぶり。2002年、打ち捨てられた仮想現実空間を舞台にした《廃園の天使》三部作の第一作『グラン・ヴァカンス』を刊行して、SFファンの度肝を抜いた。
続く作品集『象られた力』で、2005年の第二十六回日本SF大賞を受賞。さらに作品集『自生の夢』では2017年の第三十八回日本SF大賞を受賞。同じ作家が同賞を二回受賞したのは、飛浩隆が初めてであった。(飛さんの後に、酉島伝法、長谷敏司の両氏が受賞している)
飛浩隆
最新作品集『鹽津城』は、2018年から2022年にかけて発表された六篇をまとめたもの。帯に「8年ぶりの作品集」とあるのは、2016年の『自生の夢』からのカウント。18年
の『ポリフォニック・イリュージョン』は八〇年代の旧作をまとめた初期作品集だから、勘定に入っていないようだが、それから数えても六年ぶりの短篇集なのだ。
大森望編のアンソロジー《NOVA》の掲載作が一本あるだけで、それ以外の五篇は純文学系の媒体に発表されているため、幻想的なタッチで非現実の世界を描いた作品が多い。これは、眉村卓が異世界もので目指していた作風の完成形ともいうべき一冊なのだ。
大森望編のアンソロジー《NOVA》の掲載作が一本あるだけで、それ以外の五篇は純文学系の媒体に発表されているため、幻想的なタッチで非現実の世界を描いた作品が多い。これは、眉村卓が異世界もので目指していた作風の完成形ともいうべき一冊なのだ。
小川哲
新鋭枠の小川哲 は、2015年、『ユートロニカのこちら側』で第三回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞してデビュー。2017年の第二長篇『ゲームの王国』で、早くも第三十八回日本SF大賞を受賞している。飛浩隆『自生の夢』と同時受賞で、この時、選考委員だった飛さんは、自作が候補になったため、選考会へは書面での参加であった。私も選考委員を務めていたので、その回の選評を再掲しておく。
小川哲『ゲームの王国』も新鋭作家の作品である。やや未整理の目立った第一長篇『ユートロニカのこちら側』に比べると長足の進歩で、物語の孕む熱量を保ったまま、作者が作品全体を高い精度でコントロールしているのが素晴らしい。
ポル・ポト政権下のカンボジアを舞台に奇抜なキャラクターが次々と登場する上巻は、マジックリアリズムを意識していると思われるが、私は「忍者武芸帳」の影一族を連 想した。そう思ってみると、上巻の雰囲気は「カムイ伝」に近いようにも見える。
下巻に入ると一転して近未来へと舞台が移る構成の妙、「人生」と「ゲーム」を対比させた主題が明確に描かれ、小説の面白さをたっぷりと感じさせてくれる。SF味が薄い、という評もあったが、半村良『聖母伝説』のように注意深く読まないと最後までSFと分からないようなSFもあるのだから、本書も充分にSFの範疇に含まれると思う。 この作品をもっとも強く推した飛さんが、よりによって書面参加だったため、議論の途中で隔靴掻痒の感はあったものの、その飛さんの作品と並んで受賞という結果は、順当なものだったと確信している。
ポル・ポト政権下のカンボジアを舞台に奇抜なキャラクターが次々と登場する上巻は、マジックリアリズムを意識していると思われるが、私は「忍者武芸帳」の影一族を連 想した。そう思ってみると、上巻の雰囲気は「カムイ伝」に近いようにも見える。
下巻に入ると一転して近未来へと舞台が移る構成の妙、「人生」と「ゲーム」を対比させた主題が明確に描かれ、小説の面白さをたっぷりと感じさせてくれる。SF味が薄い、という評もあったが、半村良『聖母伝説』のように注意深く読まないと最後までSFと分からないようなSFもあるのだから、本書も充分にSFの範疇に含まれると思う。 この作品をもっとも強く推した飛さんが、よりによって書面参加だったため、議論の途中で隔靴掻痒の感はあったものの、その飛さんの作品と並んで受賞という結果は、順当なものだったと確信している。
小川哲
その後、第一作品集『嘘と正典』(ハヤカワ文庫)をはさんで、満洲国の架空の歴史を描いた大長篇『地図と拳』で第十三回山田風太郎賞と第百六十八回直木賞を受賞。広
く一般に、その才能が知られるようになった。
競技クイズを論理的に突き詰めてミステリにしてしまった第四長篇『君のクイズ』(朝日新聞出版)、連作短篇集『君が手にするはずだった黄金について』(新潮社)、第 二作品集『スメラミシング』(河出書房新社)と、デビュー十年で著書七作。似た傾向の作品はひとつもなく、それでいてどれも面白いという稀有な作家である。ぜひ、ご注目を!
競技クイズを論理的に突き詰めてミステリにしてしまった第四長篇『君のクイズ』(朝日新聞出版)、連作短篇集『君が手にするはずだった黄金について』(新潮社)、第 二作品集『スメラミシング』(河出書房新社)と、デビュー十年で著書七作。似た傾向の作品はひとつもなく、それでいてどれも面白いという稀有な作家である。ぜひ、ご注目を!